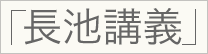『想像ラジオ』と『遊動論』(いとうせいこうと対談)
東日本大震災五周年を記念して再掲載:いとうせいこう『想像ラジオ』(河出文庫)と柄谷行人『遊動論―柳田国男』(文春文庫)をめぐって
■新しい柳田論「遊動論」はなぜ書かれたか
いとう 柄谷さんの「遊動論――山人と柳田国男」(文學界二〇一三年十月号〜十二月号。二〇一四年一月文春新書より刊行予定)をいち早く読ませていただきました。『トランスクリティーク』『世界史の構造』『哲学の起源』のあと柄谷さんが何をやるのかと思ったら柳田国男だったことに驚いたし、前作までで獲得された視座に立って柳田を読むというのが非常に面白かった。と同時に、現在の日本の政治的状況を考えると、すごくアクチュアリティがある論だと思いました。戦争の問題ですよね、これは。
柄谷 そうですね。
いとう 戦争が近づく中で「こども風土記」を書き、空襲下で「先祖の話」を書いた柳田国男に柄谷さんが焦点を当てたというのは、柄谷さんの著作のタイトルでいうと「〈戦前〉の思考」が今ますます必要になってきているのかなと思いました。
柄谷 僕は四〇年前、つまり一九七四年に長い柳田論を書いたのです(「柳田国男試論」。インスクリプト刊『柳田国男論』に収録)が、その後はあまり読んでいなかった。その柳田論はいつか書き直して出版しようと思っていたんですが、だんだんやる気がなくなった。それは一つには、そこに書いたことの多くを、『日本近代文学の起源』という本で使ったからですね。書き直すなら、それを含めて全部やり直さないといけないから、めんどくさいし、もっと違う観点からやろうと思っているうちに時間がたってしまったのです。柳田については八〇年代にも一度書いてるんですが(前掲『柳田国男論』表題作)、その頃は柳田にあんまり興味がなかったね。柳田に関しては、山口昌男、網野善彦といった人たちが理論的にリードしていて、僕はそれに対して、特に言うことがなかったんですよ。現在は、あれではだめだという観点が出てきたので、新たに書こうという気になったのです。
具体的にいうと、それは、遊動民あるいは遊動性についての新しい見方が出てきたということですが、それはやっぱり『世界史の構造』を書いたからですね。理論的な枠組みはそこにあった。ただ、そこでは書き足りなかったことを、あらためて書こうとした。『哲学の起源』もそうですね。
いとう 『世界史の構造』(岩波現代文庫)で提示された枠組みにより、いろんなものが読み直されているということですね。今回は柳田だと。
柄谷 そうです。遊動民(ノマド)といっても、狩猟採集民と遊牧民は違う。それを考えていたとき、柳田が「山人」について言ってきたことを思い出した。彼は山人と山民(山地民)を区別したのです。それで柳田について再考するようになった。それが今回の仕事をするようになった一つのきっかけです。
もう一つは、東日本大震災で多くの死者が出たことです。そのあと、柳田の『先祖の話』を読んだ。実は、一九九五年の阪神淡路大震災のときにも、『先祖の話』を読んだのです。僕は震災後まもなく神戸の辺りを歩き回ったのですが、戦後の焼け野原の時期を思い出した。柳田は空襲警報を聞きながら『先祖の話』を書いた。そういうつながりがありますね。
さらにいうと、個人的な話ですが、僕が最初に『先祖の話』を読んだのは一九六八年で、父親が神戸の海側にある病院で死にかけていたときです。病室で読んだ。柳田によれば、人は死んだら魂は「裏山」に行くという。裏山というと、眼前に六甲山があった。阪神大震災のあと瓦礫の中を歩きまわったとき、そのことを思い出した。そして、東北大震災のときにもそれを思い出したんですよ。
■『ノーライフキング』と子供のネットワーク
柄谷 僕はめったに小説を読まないのに、いとうさんの『想像ラジオ』を読んだ。実は今日は、自分のことは全然考えてこなかったのです。僕の考えは「遊動論」に全部書いてしまったので、それを読んでください、ということで(笑)。今日はいとうさんのことで話そうと思って来たのです。僕はたしか一九八八年に、あなたの『ノーライフキング』を読んだとき、「これは柳田ですよ」と言ったんですよ。
いとう はい、そう言ってましたね。
柄谷 自分が柳田のどこからそう考えたのか忘れてしまったので、今回調べてみたら、「小さき者の声」というエッセイに、それがあった。たとえば、柳田は、日本で子供が大人に、「今何時ですか」と尋ねる遊びが流行していることに気づいた。それは時間を知りたいんじゃなくて、大人が時計を持っているかどうかを賭けた遊びなんです。大正時代では、まだ腕時計を持ってない人が多かったから。しかし、日本の子供の間でそれが流行っていると思っていたら、ヨーロッパに行っても当地の子供に同じことをやられて驚いた、ということを書いている。子供の創造性や子供間での伝達の速さに注目しているんです。
子供間の噂の情報網について書かれた『ノーライフキング』を読んだとき、それを思い出した。今あの小説を読む人は、インターネットやツイッターを先取りしていたとか言うかもしれないけど、そうじゃない。そういう通信網は子供のほうがもっと先取りしてるんです。ヨーロッパまで行くのに船で何カ月もかかった時代に、子供の間の情報は信じがたい速さで国境を越え、言語の差異を越えて伝わった。
いとう 『ノーライフキング』が柳田だという意識は柄谷さんに言われるまで全くなくて、あわてて「こども風土記」などを読んだ記憶があります。「こども風土記」も、「鹿・鹿・角・何本」という遊びが、日本には明治初期にアメリカの宣教師によって伝えられたらしいけど、同じ遊びが世界中に広がっているという内容ですよね。
柄谷 子供の通信網ってそういうものでしょう。インターネットやツイッターなんかは、むしろマスコミです。そんなものはいま全部アメリカに盗聴されている(笑)。
いとう なるほど、NSAによって(笑)。
柄谷 でも、子供の通信は盗聴できないでしょう。本当の通信ネットワークというのは子供のほうにある。高度な通信技術と言ったって、結局は資本と国家のためにあるのであって、実は、それに対抗するようなものが他にある。太古からある。柳田を読むと、そういうことを考えさせられます。
■『想像ラジオ』と『先祖の話』
柄谷 『ノーライフキング』についてはそういう記憶があった。そして今度の『想像ラジオ』を読み始めて、すぐに、これも柳田だ、と思いました。作品の中に、これは柳田を読んでいなければ絶対書けない、というところが少なくとも一ぺージあるんですよ(笑)。
いとう やっぱり、わかりましたか。
柄谷 ええ。確信を持ちましたね。柳田風にいえば、「私にはほぼ証明し得られる」「いくらでも証拠がある」という感じです。
いとう 取り調べみたい(笑)。書き始めたときは柳田国男のことはまともに考えていませんでしたが、第三章に入ったぐらいから、「死者はどこに行くのか」という問題につきあたって、これは自分一人では書けないぞとなって、『先祖の話』をめくらざるをえませんでした。とくに第四章は柳田の影響が強いかもしれない。柳田以外にも死者について書いている、たとえば上原専禄の本を読みましたが。
柄谷 柳田によれば、死者は死んだ当初は個別的だけれど、時間が経つと一つの御霊(みたま)に融合する。融合しながらも個別のまま残るんですが。それが氏神だというわけです。『想像ラジオ』の人物が、自分と外界との境界線が崩れて、人格が消えて行きそうだと言うところがありますね。その辺りは、柳田でしょう。
いとう はい、第五章ですね。たしかにそこは、『先祖の話』をひっくり返し読み始めて以降に書いた章です。あそこに出て来て死者がどこに行くのかを語るキイチさんというお爺さんは、ほとんど柳田国男みたいですね。
柄谷 それから、この小説には、死者を弔うというよりも、死者と共にこの国を作り直していく、死者と一緒に未来を作るんだ、という主題があるでしょう。柳田自身、『先祖の話』を書いているときにそういう気持ちがあったと思います。彼は敗戦が近いことをわかっていたと思う。国家中枢に近い所にいた人だから。
いとう 官僚ですもんね。
柄谷 ただ、それは常識でもわかる。ヒットラーが自殺し、東京が毎日爆撃を受けてるのに、戦争に勝てると思うほうがよほど難しい。柳田が特に優れた見識をもっていたわけじゃなく、敗戦が間近だということを皆が見ないようにしていただけでしょう。今だって同じですけどね。原発事故はもう片づいたと思いたいから、それを見ないようにしている。『先祖の話』というのは、過去についての話ではなくて、これからどうするかという話だと思うんですよ。まもなく日本が敗れる、そして、多くの戦死者が外地にいる。その死者をどうするかというのは深刻な問題だったはずです。
■死者と生者のアソシエーション
いとう 新しい柳田論では、大量の死者がいるということと「遊動性」が結びつく。そこはどうなっているんでしょうか。
柄谷 『先祖の話』には、死者とともに戦後の社会を作ろうというメッセージがあった。それは二度と戦死者を出さない社会を作ろうということです。現実には、それとは反対の方向に進んだ。現在も、それがくり返されています。だから、あらためて『先祖の話』を考える必要があると思うのです。
その際、柳田に関する一般的なイメージを払拭する必要があります。たとえば、初期の柳田国男は、「山人」や各種の遊動民(漂泊民)について考えていたが、一九三五年以降はそれを放棄し、稲作農民=「常民」に焦点を移した、といわれている。柳田に好意的な人であってもそう考えています。また、柳田の固有信仰も常民=稲作農民に固有の信仰である、というのが定説です。
しかし、僕はそれに異論がある。先にもいったように、遊動性には二種類あります。狩猟採集民的なそれと、遊牧民的なそれです。後者は、武士をふくむ芸能的な漂泊民も含みます。柳田は一九三〇年代には、そのような漂泊民に対して否定的になった。それは、この時代、満州帝国があり、大陸浪人のようなタイプの遊動性が奨励されるようになったからです。そのとき、柳田は「常民」や「一国民俗学」を言った。しかし、それは狩猟採集民的な遊動性を否定することではありません。その意味で、彼は「山人」を放棄しなかった。ただ、彼は、遊動民=山人を祖霊のほうに求めたのではないか、というのが僕の考えです。
いとう 祖霊のほうが遊動しているというのは?
柄谷 柳田がいう固有信仰では、こういう感じです。あの世とこの世の間に自由に往き来があり、そしてお互いに面倒を見ている。つまり、死者と生者とのアソシエーション(連合)がある。
いとう そうか、アソシエーションの問題がそこまで広がるんですね。僕も『想像ラジオ』を、死者を供養するつもりで書いていたら、いつの間にかアソシエーションのことになっちゃったんです。
柄谷 生きている方は死者を祀るが、死者も無条件でこっちを見守っている。こういう信仰は、実は、稲作農耕民にはないんです。この世が階級的だから、あの世も階級的になっています。また、神強制(祈願)というか、呪術的な見方が強くなる。このことは、世界各地の先祖信仰を調べるとわかります。
ところが、柳田がいう固有信仰では、祖霊は、身分、血統、生前の業績などでは区別されない。神への祈願もしない。祖霊である神への絶対的な信頼がある。これは遊動的な狩猟採集民の社会から来るものだと思います。このような固有信仰では、いわゆる普遍宗教でも実現できないような信仰の境地が実現されている。だから、固有信仰はプリミティヴだということはできない。
いとう そっちのほうが普遍的だという結論ですね。
柄谷 ええ。むしろそれこそ、普遍宗教だと思うんです。だからこそ、柳田は固有信仰を求めていた。
いとう 遊動という言葉から僕が連想するのは、柄谷さんがデモの現場に出て行ったことで、歩くことは遊動だから、その歩くという行為が、人類にとって基本的な何かを取り戻すような感じがあるんです。
富田京一さんという在野の生物学者と話していたら、人類の骨格的な特徴を一つ挙げるとすれば、たらたら移動できることだと。ほかの動物はある時間休んでいないといけないところを、人間はたらたらと海辺を移動しながら、浜に上がったものを食べていたんだろうと。
柄谷 それはなかなかいいですね。ただ、遊牧民は走るからね。それも馬に乗って走るから速い。のろのろ歩くのでないとだめですよ。
いとう そうやって歩いて移動することによって、ひょっとしたら自分のなかにある遊動性が掘り起こせるのかなあと。
柄谷 僕は、遊動性は定住したときにも保持されうると思う。遊動的な状態ではだいたい生産物は共有され、平等に分配されます。蓄積できないからです。定住しても、そのような共同所有が残る場合、遊動性が残っているといってもよい。だから、形態だけで遊動的か定住的かを区別する見方はだめだということですね。
いとう なるほど。動いてなくても遊動性はある。それはドゥルーズ=ガタリのノマドロジー批判ですね。
■双系制をめぐって
柄谷 先祖崇拝に話を戻すと、今回調べたら、世界各地にある先祖崇拝はほとんど父系制にもとづいている。そして、そこでは、生者と霊との関係も父系制的なんですね。つまり、祖霊と子孫のあいだに敵対性がある。
いとう 抑圧と憎悪ですね。
柄谷 そう、すごくエディプス的なんです。一方、母系制は違うようにみえますが、母系制社会にも父子の葛藤がある。母系社会は必ずしも母権社会ではない。むしろその逆で、たいてい父親が実権をもっています。たとえば、未開の母系社会では父親が妊娠の原因であるという知識がないことが多い、といわれる。つい最近まで、その通りだと思いこむ学者が多かったのですが、スパイロという人類学者がそうでないことを示した。父親が妊娠に関係していることを知らないのは、精神分析の用語でいうと父親の介在を「否認」することであり、それ自体、父親に対する敵意を示すものである。それは「自分は父親と何の関係もなく生まれてきた」という主張になるわけです。だから、母系社会でも、父と子の葛藤は強く存在するんです。
ところが、父系や母系といった系列が意味をもたない親族制がある。それが双系制です。もともと遊動民のバンド社会では、母系も父系もない。その意味で、双系制には古い形態が残っていると思います。双系制ではむしろ、血縁関係がなくても構わない。つまり、養子でもいいし、年齢や性別も問わない。家に何らかの関係がある者は皆、先祖になる、というのが、柳田のいう固有信仰ですね。
いとう いちばん自由なんですね。
柄谷 双系制という見方は、一九七〇年代に東南アジアの人類学的研究にもとづいて出て来た。それまでは、十九世紀半ば以来、親族形態は最初は母系制で、やがて父系制に移行したという説が支配的でした。日本でも、高群逸枝が母系制が先行したと主張して、柳田国男を批判したのです。しかし、それは間違いで、父系、母系のどちらでもない双系制があったということになった。そこから見直すと、柳田が正しかったということがわかります。柳田がいう固有信仰、つまり、遊動民の社会では、出自や血縁はどうでもよかった。最近気がついたんだけど、北欧の家族関係は今やそういう状態に近づいてますね。
いとう そういえばこの間、スウェーデンのコメディ映画で「クリスマスイブは大騒動」(一九九九年、シェル・スンズヴァル監督)というのを観ました。主人公の女の人がクリスマスの晩餐に元夫三人を招待するんだけど、彼らもそれぞれ結婚相手を連れてきて、大騒動になる。ゲイも出て来るし、北欧では家族がこんなに多様化しているのかと、びっくりしました。
柄谷 それは新しい形態というよりも、昔あったものが回帰しているんだと思います。それに対応して、宗教も違ってくるでしょうね。
いとう 誰を祀るかが違ってくるということですね。
柄谷 たとえば、日本では、死んで何年も経つのに法事がありますが、いったい何回忌までやれば気が済むんだ、と思いませんか。柳田の考えに従えば、もうその人の霊は存在しないというのに。
いとう なるほど、一つの御霊に融けこんじゃってるから。
柄谷 それに、固有信仰では、先祖として特別な個人を重視してはいけないんですよ。だから、一定の故人の法要を何回もするのはまちがっている。そんなものは仏教が勝手に作った制度にすぎない。ただ、今回僕が気づいたのは、柳田が、古来からの信仰が仏教によって歪められたということを、あまり批判的にいわないことですね。それは固有信仰を維持することが難しいと考えていたからでしょう。たとえば、同じ村にずっといるならいいけれども、人は移動しなければならなくなる。「裏山」がないような所にも住まねばならない。そういうときに、仏教のような外来の宗教が必要となった。その意味では、仏教のおかげで先祖信仰が残ったとも言えるんですね。
■死者の養子になるとは
柄谷 僕が『先祖の話』で長いこと疑問だったのは、最後に書いてある提案です。死者の養子になることで、彼らを先祖にしよう、というところ。
いとう あれはすごいですねえ。
柄谷 この場合、死者は、たいがい若くて、二十歳かそこらだと思うんです。彼らを靖国神社などではなくて、各家で先祖にしてあげなければならないと柳田はいう。そのためには、死者の養子にならねばならない。しかし、それは事実上、自分よりも若い人の養子になることです。そんなことができるのだろうか。
いとう ああ、実際に死んだ年を言っていたら……。
柄谷 そのことがずっと疑問だったんだけど、今回はっきりわかったんですよ。双系制なら、そんなことは関係ないんだと。性別も不要であると。
そういう親族形態は、たとえば歌舞伎の世界には残っていますね。僕は最近、歌舞伎関係の人たちと会ったのですが、血縁にとらわれない彼らの考え方に驚嘆した。なんでもあり、というか。スウェーデンのはるか先を行っている(笑)。
いとう 歌舞伎役者の人たちと一緒に大部屋にいると、彼らは「おじさん」「お兄さん」といった親族関係の呼称をすごく自由に使うんですよね。「これはおじさんに聞いた型だ」とか。と同時に、仕草がおばさんっぽかったりして、男といる感じがしない。そして、抵抗なく養子に行く。
柄谷 それは歌舞伎界の特徴ではなくて、日本の双系制がつくり出したものだと思う。
いとう 職人の世界もそうですね。大阪の芸能だと、文楽がそう。血統が一切関係ない実力主義で、誰それの何代目を継ぐと。歌舞伎以上にはっきりと養子制をとっている。
柄谷 柳田は、オヤ・コというのは労働組織にもとづくと言っている。親分・子分ですね。そして、親分こそ真のオヤで、血縁の親は「産みのオヤ」にすぎない。中国・韓国などと日本では、そこが本当に違うなあと思います。儒教では「忠」より「孝」を重視しますが、日本で忠を重視する。しかし、それは孝行に反するわけではない。忠とは親分に孝行することだから、親孝行なのです。だから、日本ではいつでも忠が勝つ。中国・韓国では親が勝つけど。
いとう 血統が勝つということですね。
柄谷 ええ。儒教の体系ではそれが前提になっています。その意味では、日本に儒教が根づくわけがないんですね。オヤを親と漢字で記したために、錯覚が生じたんでしょうね。
いとう 歌舞伎の「菅原伝授手習鑑」の「寺子屋」というのは、主君のために自分の子供の首を切らせちゃう話ですが、これはどういうことだろうと思っていたところ、「遊動論」を読んで腑に落ちたんです。
柄谷 それは親孝行なんですよ。
いとう 親分に対しての孝行ということですね。
柄谷 そう。たとえば、『三国志』では、徐庶という軍師が、年老いた母親からと偽って送られた手紙に騙されて、劉備の下を去って曹操に仕えるため親元に帰る。そのことに劉備も納得するんですね。
いとう ああ、お母さんだから仕方ないと。
柄谷 徐庶は最後に劉備に、孔明という天才がいることを言い残して立ち去った。しかし、帰ってみると、母親は私がそんな手紙を出すわけがないと怒り、情けない奴だと言って自決してしまう。しかし、結局、彼は曹操のところにとどまった。僕は子供のころから、この話のことをよく考えましたね。日本だったら、そんな手紙を母親が出すはずがない。出しても子供が帰るはずがないから。だけど、中国では母親に呼ばれたら帰るのは当然だと思われており、それが許される。息子を叱った母親は忠義を重んじる人として称賛されますが、親の元に帰った徐庶のほうも孝行者として偉いと考えられる。それに比べて、日本では、孝は忠には対抗できないと思う。
いとう 対幻想が勝利しない。
柄谷 そうですね。
いとう 血でつながった親子の情が忠義の前に敗れるというのは、日本の芸能のいろんな演目が繰り返しテーマにしている感じがありますね。産みのオヤより親分の方が大事という教育のためにやってるとしか思えないぐらいに。「義理と人情」を「義理・アンド・人情」だと思っている人が多いけれど、義理と人情がぶつかって、義理が常に勝つという話ですからね、ほとんどあらゆる物語が。
■小さき者の目で
いとう 「遊動論」の最終章の結び部分に、「小さいこと、あるいは、弱いことは、普遍的であることと背反しない」と書かれていますね。これは固有信仰が、小さき者、子供のことと結びついているように思ったんです。
柄谷 そうですね。「大きいこと」「小さいこと」は、言葉についてもある。大きい言葉と小さい言葉、それはいいかえれば、「書かれたもの」と「話されたもの」ですね。さらに、書かれた言葉による歴史と、書かれない言葉による歴史。柳田は、自分が考えてみたいのは南北朝とか室町とか江戸といった区切りが明瞭に存在しないような歴史だと言っている。そのような区切りはたんに政治的権力の次元で変わったけで、多くの人の生活の次元では何も変化はない。「はい、今日から徳川時代です」というように変わるわけではない。
いとう なるほど、民衆はそうですね。
柄谷 政治的事件や偉人を軸とする歴史とは違った歴史があるという柳田の考えは、現在では普通に受け容れられていると思います。しかし、柳田がのちに「実験の史学」と呼ぶようになった史学を始めたのは一九二〇年代で、これはちょうどフランスでアナール学派が始まった頃です。だから、柳田が『明治大正世相史篇』などでやったことが民俗学的方法をとった歴史学だということは、同時代にはわからなかったでしょう。日本人が柳田の史学についてわかるようになったのは、もっと後で、実はアナール学派を通してだと思う。
しかし、僕はアナール学派を読む前に柳田の史学を理解していた(笑)。というのは、アナール学派の仕事を読んだ時、これは柳田と同じじゃん、と思ったからです。たとえば、僕は一九七〇年代に『日本近代文学の起源』に「児童の発見」という章を書いていますが、あれは完全に柳田に拠っています。しかし、あとで、それを僕がアナール学派の誰かを剽窃したと言う学者がいたのにはあきれました。
■『想像ラジオ』ではなく「現実ラジオ」だ
いとう なぜそのことを聞いたかというと、柄谷さんは、さまざまな違うことをやっているように見えるけど、たびたび児童のことを書いてるんですよね。「遊動論」にも何度も子供のことが出て来るのが面白い。今わかったのは、あ、それは柳田の視線か、と。語られないこと、力を持たないもののことを常に考えないと、実際に動いている歴史が見えないということでしょう。つまり、児童の目になって見ることなんじゃないかな。
柄谷 うまく言いますね(笑)。
いとう 『想像ラジオ』が出てしばらくして、あるとき柄谷さんから突然、「あれは想像ラジオじゃなくて、現実ラジオだ」と言われたんです。柄谷さん、覚えてないでしょう。
柄谷 覚えてない(笑)。
いとう つまり柳田は、死者と生者が交流する世界を、想像とは思っていなかったはずだと。
柄谷 そう、実在だと思っていたでしょう。たとえば、吉本隆明はそれを「共同幻想」と言ったのですが、違うんですよ。柳田にとってあの世は実在する。カントの言う「物自体」がそれにあたります。たとえば、僕は霊能者に何人か会ったことがあるんですが、僕のオーラの色を尋ねると、彼らが言う色は皆違う(笑)。しかし、ゆえに全部幻想にすぎないかというと、そうとはいえない。たぶん、オーラのような物はある。しかし、それを色として見る場合、感性によって構成された「現象」となる。が、それはまったくの幻想(仮象)なのではない。カントが物自体・現象・仮象という区別をしたのは、本来、こういう問題からです。
いとう そこは神秘主義との違いをはっきりさせないと、すごくきわきわな……。
柄谷 ええ。僕がカントの霊界についての考えに関心を持ったのは、一九九五年阪神大震災のあとで、まもなくソウルで開かれた建築家の会議でそのことについて講演したのです。カントはリスボン大地震の後にスウェーデンボルグのことを考えるようになったんですよ。
いとう スウェーデンボルグは、霊視者ですね。
柄谷 そうです。もともと著名な自然科学者だったのですが、この地震を予言したことで有名になった。カントは地震について科学的な仮説を立て耐震建築に必要を語る一方で、スウェーデンボルグの霊界論について考え、「視霊者の夢」という奇妙な論文を書いた。これも、地震が大きなきっかけになっているのです。
いとう それは大量の死者がいるという、危機ということですね。
■死者の国は地底ではない
柄谷 『想像ラジオ』に即していえば、あるものが「想像ラジオで」しか聞けないとしても、それは幻想だということにはならない。実在ではあるが、想像ラジオという装置でしか聞けない、ということですね。
死後の世界について、柳田がこういうことをいっています。日本では、死後の世界は地底にあると考えられてきた。『古事記』にそう書いてあるから。しかし、柳田の考えでは、ネノ国はもともと、山の上あるいは上空にあると考えられていた。ところが、ある時点で「ネ」に「根」という漢字を当ててしまったために、魂が地底に行くような意味になってしまった。本居宣長はそれに気がついていたが、疑問を呈するだけに終わった。それは宣長が「実験」、つまり、現在残っている各地の言葉を調べようとしなかったからだと、柳田はいうのです。漢心からできるだけ離れようと主張したにもかかわらず、宣長はそれができなかった。文献だけに頼ったからです。一方、柳田は沖縄に行った。沖縄では、あの世は地底ではない。
いとう ニライカナイがありますからね。
柄谷 ええ、それは海の向こうにある。とにかく、ネもニライも同じもので、当然、地底ではない。一方、仏教では、あの世は非常に遠いところにあります。日本の仏教では、遠い浄土に行った霊がお盆になると帰ってくる。なんでそんな遠いところから帰ってくるのかと思いませんか(笑)。
いとう まあ、遠いですよね、西方浄土は。
柄谷 たとえば、最近日本でも定着したアイルランド系の祭り、ハロウィーンがあるでしょう。あれは日本でいうと、地蔵盆にあたります。地蔵は子供です。子供が力を取り戻す日なんです。
いとう なるほど、王権に逆らう日みたいな。
柄谷 子供が力をもつ祭式がある。それに仏教的な色付けをすると地蔵盆になる。そのような風習は各地にあります。ヨーロッパの民俗学はもともと、習俗などに残っているキリスト教以前の宗教を研究するものとして始まった。柳田はそういうことをよくわかった上でやっています。彼はもともとハイネを読んでいたから。
いとう 「遊動論」のあの指摘は驚きました。マルクスと親しかったハイネを通じて、柳田がマルクスとつながってくるというのは。しかも「共産党宣言」の冒頭は「一つの妖怪が……」ですもんね。すごく面白い。
柄谷 あくまで僕の説ですけどね。「遠野物語」が書かれた頃には妖怪に関する本が流行っていたんですよ。柳田の妖怪論はそれを含むんですが、それとは根本的に違うものがあるとも思います。今回、柳田が宮崎県椎葉村の焼畑狩猟民を見て、そこに「社会主義」を見いだしたという話を書きました。椎葉村の人たちは「山民」であって、山人とは違って平地の人にも理解できる人たちですが、まあ、山の中でこういう人たちに出会ったらほとんど妖怪に見えるよね。
いとう 今でも、山の中の寺を見に行くと、山岳宗教の人たちが白装束で山道を歩いてるのに出会うことがあって、それはこの世のものに見えないです。何か怪異なものに見えても不思議ではない。
柄谷 先ほどカントについて話したように、ひとが山中で天狗のようなものを見ることがあっても、それをたんに幻想として片づけることはできない。たとえば、真珠湾攻撃の後、アメリカ人は日本人を恐ろしい存在として想像したと思う。当時のアメリカの漫画に描かれたジャップの姿は、いわば彼らの天狗みたいなものです。そんなものは存在しないからと言って、日本人が存在しないわけではない。それと同じことです。
いとう 現れとしてそう見えるということですね。
■三陸沖地震と柳田
柄谷 ところで、柳田も地震のことを何回か書いています。「遠野物語」第九十九話で、大津波で妻を亡くした男が、一年後に妻を見かける。彼女は別の男と一緒にいて、それは彼女が結婚前に好きだった男らしい。うれしそうにしているので、遺された子供が可愛くないのかと妻に問いかけると、悲しい顔をして立ち去った。それを追いかけようとして、あ、そういえば死んでたんだ、と気がついたという話。これは明らかに三陸沖地震なんです。とにかく、人が死ぬと、それがたとえ大量でなくても、われわれはその死者との「関係」について考えざるをえない。
いとう カントの「物自体」と実在のことをもっとうかがいたいです。なぜなら、『想像ラジオ』は結局心霊の話で、神秘主義じゃないかと言う人がいるんですが、僕はまったくそのつもりはないんですね。だけど、じゃあ科学かというと、そうとも言えない。
柄谷 カントの考えは、通常、科学認識論の問題として考えられていますけど、彼の関心はそれだけではなくて、最初から、魂のことにあった。物自体といっても、むしろそれを霊魂のことだと考えないといけない。霊魂あるいは霊界は経験的には把握できない。しかし、それは実在する、とカントは考えた。つまり、それが物自体です。
いとう 死者の世界は「物自体」だと。
柄谷 そうです。経験的にはつかめないが、だからといって、それがないということにはならないんですよ。
いとう あるとも言えないということですか。
柄谷 積極的に経験的に、あるということはできない。カントは「物自体」というものをいつも弁証論的に示しています。つまり、そのように考えなかったならば、背理に陥るという形で。昔、僕もそういうことを考えていたんですが、一例を言うと、こういうものです。「あの世」は存在する。なぜなら、「この世」は、「あの世」がなければ存在しないからだ。
いとう そこなんですよ。僕も理論的に考えていったら、第四章でそうなった。死者がいなかったら生きているということも成立しないと。生者と死者は持ちつ持たれつで、一方的な関係じゃないという結論になったんです。
第一章である声がラジオに乗っかってくるんですけど、実はそれは津波に関係ない可能性がある死者のものなんです。それによって、あるときに亡くなった人だけではない人たちのラジオになる。死について考えるうちに、一つの災害に限定せずにもっと広げなければならないと思ったんでしょうね。
柄谷 それは広島、長崎までつながる。
いとう そういうことです。さらに東京大空襲のことも考えざるをえなくなって、あらゆる死者を放っておけないことになっちゃった。
柄谷 先に言いましたが、阪神大震災の後に神戸で瓦礫の中を歩いて思ったのは、僕が子供のときに見た焼け野原の神戸に似ているということです。あそこにいた年寄りはみんなそう思ったと思います。なんか、もとに戻ったという感じがあった。底が抜けたような感じがあったね。
二〇一一年の一月に、僕はいとうさんと奥泉光さんに呼ばれて近畿大学で『世界史の構造』について講演をしたのですが、そのとき、交換様式Dが未来だけでなく、あるいは宗教だけではなく、現に在るのだといった。その例として、レベッカ・ソルニットの『災害ユートピア』という本をとりあげたのですが、その際、阪神大震災のことを話しました。その二カ月後に東日本大震災が起きるとは思いもよらなかったけど。この地震のあとまもなく思ったのは、今度の地震では「災害ユートピア」は成立しないだろう、ということでした。
ソルニットは、「災害ユートピア」が成立しなかったケースは、国家が軍を派遣して介入した場合だといっています。福島原発の場合、軍や警察は介入していない。ただ、放射能が人を切り離した。しかし、原発はそもそも国家によるものです。だから、放射能というよりも、国家が「災害ユートピア」を妨げたのだと思います。
いとう 放射能という形で国家が出てくると、ひじょうに捉えづらいですよね、本当に。
柄谷 『想像ラジオ』に、福島の原発事故のことは入っていましたっけ。
いとう ちょっとだけ入っています。放射能によって人が住めない土地になってしまったという噂があるというのを、語り手の父親が言うんです。
柄谷 ああ、そうでしたね。僕は、このラジオはレディオアクティビティ(放射能)の意味なんじゃないかとも思った。
いとう もちろん、その二つの意味があります。だから、語り手が裏山に帰るラストシーンは、ハッピーエンドとは限らないんです。だって、放射能で人がいない可能性があるわけですから。先祖だけが山へ戻ったら、人がいなかったという可能性を含んでいると思ってます。はたしてこれはどっちのエンディングなのか、作者からは言わないでおこうと。
柄谷 そうか。『ノーライフキング』のときもそうだったけど、僕は特に近年はめったに小説を読まないのに、『想像ラジオ』だけは読んだ。なんか不思議な気がしました。ちょっと別次元のものを感じたんですよ。だから実は、芥川賞の候補になったときは驚いた。
いとう もう新人じゃないですもんね。
柄谷 まあ、それはいいとして、もっと驚いたのは落ちたことだよ(笑)。選考委員は何考えてんだ、と思った。同時に思ったのは、このような作品は、時代状況によることが明らかであるにもかからず、それによって出てくるようなもんじゃない、ということです。『ノーライフキング』もそうだった。そして、それは、両方とも柳田的主題に関連しているということと切り離せないですね。
■「楢山節考」との比較
柄谷 僕の経験では、こんなものがなぜいま書かれたんだろうと思わせる小説が一つあって、それは深沢七郎の『楢山節考』です。深沢七郎はある意味であなたと似ているね。彼は芸人だった。
いとう 音楽の人ですしね。自分で作詞作曲してますからね、『楢山節考』は。
柄谷 そして、『楢山節考』も柳田国男でしょう。
いとう なるほど。母親を山に置いてくる話ですもんね。
柄谷 ええ。深沢七郎は柳田を読んでいなかったと思うけど、だからこそ柳田的であった。柳田は「親棄山」という論文で、日本各地にある、親を棄てる話を考察しています。「親棄山」の話にはだいたい四通りパターンがあって、四通りとも最後には息子が母親を連れて帰る。だから、これは親不孝の話じゃなくて親孝行を勧める話だと柳田はいうんだけどね。
その四番目がすごい。背負われた母親が山へ向かう途中に木の小枝を折ったりしているので、何のためにそんなことをするのかと息子が聞くと、お前が帰るときに道に迷わないようにしているんだと。これは、「奥山にしをる栞は誰のため身をかき分けて生める子の為」という歌になっています。この老女の歌を聴くと亡き母を思い出して、孝行が足りなかったことを嘆かずにいられない、と柳田は書いています。むろん、この話でも、親の愛に感動した息子が、母を連れて帰るんです。
深沢七郎の書いた作品はその四通りのどれにも合わない。だって、親を山に置いてくるわけだから。しかし、ある意味では「母の愛」というこの昔話の主題をもっとも鋭く掴んでいると言えます。連れて帰らなかった者のほうが、罪の意識が深いわけだし。
いとう お母さんは最初からそれを望んで、文句を言わずに山に残るんですものね。息子に早く行け、と背中を押すんですから。
柄谷 これは当時いわれたような、反ヒューマニズムとかいうようなものではまったくなくて、究極的な母の愛をあらわすものです。深沢七郎は本気でそう考えていたと思います。とにかく、こういう作品は、時代状況がどうこうじゃなくて、ずっと古くから流れている地下水脈からパッと湧き出てきたような感じがあった。いとうさんの小説もそういう感じがするんですよ。だから、今年度ベスト3とか、そういったたちのものではない(笑)。
いとう なるほど、年度の問題じゃないと(笑)。
柄谷 『ノーライフキング』から二十五年ですか。
いとう そのぐらい経ちますね。すごく面白かったのは、芥川賞にノミネートされた後に柄谷さんに会ったとき、「よかったね」と言われたあとに、「きみはどういう運勢をしてるんだ」と。それは、僕にとっていちばん納得のいく言葉でした。『ノーライフキング』からしばらく後、スランプで十何年書けなくなって、そしていま急にこういうものを書いてる自分に対し、「どういう運勢をしてるんだ」と言われたのはすごくしっくり来た。
■「オルフェ」と『想像ラジオ』
柄谷 もう一ついとうさんに聞きたかったことがある。あなたはジャン・コクトーの映画『オルフェ』を観た? あれ、「想像ラジオ」でしょう。
いとう なるほど! そうですね。昔観ましたが、映画のことは全く考えていませんでした。
柄谷 映画『オルフェ』では、冥界からの暗号のような通信が車のラジオからやってくる。ラジオが死後の世界と生きてる者とをつなぐ通信手段なんですね。一九五〇年の映画だから、まだラジオが新しいメディアだった頃です。
いとう 今はむしろ古いメディアだと思われていますね。
僕がラジオを選んだのは、結局、聴力がいちばん原始的で、幻想的な感覚に近いから。あと、やっぱり自分の音楽好きが反映していると思います。
舞台裏を話すと、津波の被災地に行ったときに、あの杉の樹に引っかかって亡くなっていた人がいたという話を二人の人から聞いて、取り憑かれちゃったんです。その人のことを書かなければと。自分はもう十六年間小説を書いてないけれど、ここで書かなかったらもう一生書くことはない。このことをなかったことにして他に書くべきこともないと。
何とかしてこの樹上の人を喋らせたいと考えていたときに、夜、被災地を車で移動中、南三陸のあたりで、信号しか明かりがない暗闇の下のほうから、ワーワー雑音が聞こえるような気がしたんですよ。たぶんそのときに「ラジオなら出来る」と思ったんじゃないかなあ。はっきり覚えてませんが、そのときカーラジオがかかっていたかもしれない。『ノーライフキング』のときと同じで、タイトルは早めに決まっていた。「想像ラジオ」だと。その後DJの口調はどんな感じなのか、NHK「ラジオ深夜便」みたいなのか、あるいはもっと軽いのかとか、ずっと考えた結果ああいう感じになりました。
柄谷 映画『オルフェ』はギリシャ神話のオルフェウスの話にもとづいていますね。日本神話のイザナギ・イザナミみたいな話です。しかし、なんでイザナギ・イザナミ神話がギリシャ神話と同じなのかはわからないらしい。
いとう さっきの子供の遊びのような伝播の仕方だったのかもしれない。
柄谷 そうなると、さっきいった「根の国」=地底の国という考えは外来であったということになりますね。とにかく、そういうこともあって、『想像ラジオ』を読んだときに日本文学という感じがしなくて、これは世界文学だという気がしたんです。
■回帰する交換様式D
いとう 『トランスクリティーク』におけるアソシエーション、あるいは『世界史の構造』における交換様式Dが実際はどういうものなのか、柄谷さんに会ったときに何度かうかがいましたが、今回『遊動論』に収録される予定の付録にははっきり、国家が形成されることを回避する氏族社会のシステムが、強迫的に回帰するのだと書かれています。それって、日本人の固有信仰こそが、国家を超えるものということですよね。最古の形態であるとともに、未来的であり、普遍的であると。未来的というのがすごいと思う。それはつまり、再起するということですもんね。
柄谷 岡倉天心が『茶の本』で、「西洋人は、日本が平和な文芸にふけっていた間は、野蛮国と見なしていたものである。しかるに満州の戦場に大々的殺戮を行ない始めてから文明国と呼んでいる」と書いていますが、ふつう国家ができると文明だと言われる。一方、氏族社会は「未開」だと言われますが、国家が形成され階級社会になってしまうことを避ける氏族社会のシステムは、ある意味高度な文明です。生産様式やテクノロジーだけで、未開と文明を区別してはいけない。狩猟採集民が持っていた遊動性はいずれ、フロイトが言う「抑圧的なものの回帰」としてやって来ます。それは望んでそうなるのではなく、向こうから来る。
いとう なるほど、望むと望まないにかかわらず来ると。
柄谷 そういうのは幻想にすぎないというけど、そんなことはない。向こうから来る。君たちは賢くなったつもりだろうけど、愚かな幻想に捕まってるだけなんだ。そのことを教える者が向こうから来る。どんな形で来るかわからないけど、来る。災害を通しても来る。……と、だんだん「想像ラジオ」になってきた(笑)。
いとう そうか、この小説も、死者の声は向こうから来るんです。DJが「リスナーからメールが届きました」と言ってるけど、向こうから勝手に来てる。
柄谷 この小説自体が向こうから来てるんですよ。地震について書こうとした人はたくさんいると思うけど、だいたい生きてる側から書くと思う。そうなると、だんだん忘れていく方向に行くよ。忘れるために書くんだから。だけど、これは違う。向こうから来る。放送されてくる。
いとう DJも死者ですしね。彼は「お便りください」とはたぶん一回も言ってない。呼びかけもしないのに来ちゃって、しょうがないからしゃべっているのがこのラジオだから。きっと、書いてる僕自身がそうだったんでしょう。
柄谷 その声を聞き取るには、マルクスの言う「抽象力」が必要です。死者のことは抽象力でしかわからない。たとえば、物が在るとしても、物と物の「関係」は在るのか。それも在るはずですが、物が在るように在るのではない。死者はいわば、「関係」のようなものです。死者を感じるには、一種の抽象力が必要です。それが、この小説が読者に要求していることだと思います。
ここでは、生者と死者が話しているのか、死者同士が話してるのか、あるいは、そこに生者が加わっているのか、よくわからない。それはいわば、物が在ると同時に、物の関係も在るような世界ですね。その意味で、『想像ラジオ』は抽象の世界だと思う。だから、「抽象ラジオ」だね(笑)。
いとう アブストラクト・ラジオだ。ありがとうございました。
〈二〇一三年十月二十八日収録〉
『文学界』二〇一四年一月号掲載