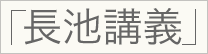近代批判の鍵
坂部恵氏は、一九七六年一月に『仮面の解釈学』、同六月に『理性の不安―カント哲学の生成と構造』を出版している。刊行は前者のほうが少し早いが、所収論文は後者のほうが早く書かれている。つまり、この二冊は、ほとんど同時に書かれ、同時に出版されたといってよい。しかも、たまたまそうなったのではない。それは、意志的になされてきたことの必然的な結果なのである。
この二冊は連関しつつも、ある意味で異質な著作である。『理性の不安』はカント、つまり、西洋哲学の可能性をめぐる本である。それに対して、『仮面の解釈学』は、日本と日本語で哲学することが可能か、可能だとしたらいかにしてかを問うような本である。日本で哲学を志す者なら、西洋哲学を目指すだろう。しかし、自分が日本と日本語という現実の中にあるということを無視することはできない。ゆえに、誰でも早晩その問題に直面する。その場合、幾つかのタイプがある。大きく分ければ、一つは、西洋の哲学が普遍的であると考え、その水準に追いつき追い抜こうと試みる人たちである。もう一つは、西洋哲学の普遍性を疑い、日本あるいは東洋で形成されてきた思想に普遍性を見出そうとする人たちである。彼らは、近代西洋の行き詰まりを超える途を、日本あるいは東洋に見出す。
坂部氏はそのどちらでもない。氏は、西洋に由来するものであろうと、近代国家と近代資本主義という意味での「近代」に、われわれが否応なく属しているという認識から始めている。このような条件は考え方を変えたぐらいで超えられるものではない。さらにいえば、坂部氏は、日本に回帰するまでもなく、はじめから日本の中に立っている。だが、日本および日本語による経験がそのままで普遍的であると考えたりはしない。ただ、それは普遍的な認識のために重要な貢献をなしうる、と考えるだけである。その意味では、日本の外に立っている。とはいえ、このように、日本の中にあり且つ外にあるというアンチノミーは、論理的に解決することはできない。これを解決するためには、いわば分裂を生きるほかない。ほぼ同時に出版された二冊の本が示すのは、そのような生の在り方である。
坂部氏が二冊の本を出した一九七六年といえば、私はその前年から、イェール大学で近代日本文学について教えていた。『日本近代文学の起源』(一九八〇年)に書いたような事柄はこのとき考えたのである。この著作の中で、私はもっぱら日本の事例を扱っているが、私が考えたかったのはむしろ西洋の近代のことである。当時は日本でもアメリカでも一般に、明治の日本文学は西洋近代文学の歪んだ受容として見られていた。しかし、私は逆に、日本の近代化という短期間の出来事の中に、歪んだ西洋近代の諸問題が圧縮されて現れていると考えたのである。
さらに、私は、近代文学の批判において、前近代(中世・古代)に回帰することは的外れだと考えた。なぜなら、そのような中世や古代のイメージは近代文学によって構築されたものであり、そのようなものでは近代の枠組を出ることにはならないからだ。そのとき私が思ったのは、近代文学批判の鍵は、広い意味では近代文学に入るにもかかわらず、そこでは周辺的なものとして排除されてしまったものにあるということであった。
その一例は夏目漱石の文学である。漱石は近代文学の中にありながら、それに対する違和を感じていた。彼は一九世紀半ばに確立された西洋の小説を好まず、同時代のイギリスで軽視されていた一八世紀のスウィフトやスターンを高く評価していた。しかも、彼はそのような文学を、日本で正岡子規の俳句運動から始まった写生文と結びつけていた。というより、むしろ、そのことがスターンなどを評価する視点を与えたのかもしれない。漱石は、自然主義文学とネオロマン主義文学が全盛の最中に、『吾輩は猫である』を発表した。日本の文壇が彼を承認したのは、彼が晩年に自然主義的な作品『道草』を書いてからにすぎない。さらに、漱石を擁護した批評家たちも、漱石が初期の作品から「発展」したという見方を少しも疑わなかった。しかし、私は漱石の中に、それ自体近代文学でありながら、しかもそれを根本的に否定するような文学の可能性を見ようとしたのだった。
私が坂部氏の『理性の不安』に収められた諸論文を読んだのは、以上のようなことを書いていた時期である。カント論に関して、私はこの本から決定的な影響を受けた。私の『トランスクリティーク…カントとマルクス』という著作は、『視霊者の夢』からカントの可能性を見る坂部氏の本なしにありえなかった、といっても過言ではない。しかし、最初に『理性の不安』を読んだとき、私はむしろそれを文学評論として読んだのである。というのも、坂部氏は、カントの『視霊者の夢』に関して何よりも、「自己を嘲笑する」ことから始めるカントの書き方に注目していたからである。氏はそこに、ディドロやスターンの文学との共時的な類似を見出している。一八世紀の小説では、サタイヤや書簡体など多種多様な表現形式がとられたが、一九世紀に「三人称客観」の手法が確立したとき、それらは未熟な形式として抑圧されてしまった。
「三人称客観」の視点は仮構であるが、それはカントでいえば、「超越論的主体」という仮構に対応するものである。逆にいうと、カントが超越論的主体を仮構した時点で、小説に生じたのと同じことが哲学におこった。坂部氏がとらえたのはそのような変化である。『視霊者の夢』に見られるカントの「理性の不安」や多元的分散性は、『純粋理性批判』では致命的にうしなわれてしまった、と坂部氏はいう。カントの柔軟な思考と文体は、「学校の文体といわば妥協し、伝統的な形而上学の枠どりに何らかの程度復帰して、自己の思考の社会化に乗り出すと同時に、必然的にうち捨てられることになる」(「カントとルソー」{本全集第巻}p232)。
とはいえ、坂部氏は、『純粋理性批判』よりも『視霊者の夢』のほうが重要だといっているわけではない。坂部氏がいいたいのは、『純粋理性批判』あるいは「批判哲学」は、それよりも前の『視霊者の夢』から見るとき、別の可能性、つまり、近代哲学を超える可能性をもちうるということである。すなわち、坂部氏は、近代批判の鍵を、近代以前にさかのぼるかわりに、十八世紀半ば、すなわち、啓蒙主義とロマン主義の境目の一時期に求めたのである。そこでは、もはや啓蒙的合理性が成り立たなくなっている。にもかかわらず、そこであくまで啓蒙的スタンスを維持しようとするならば、「自己嘲笑」的なスタイルによってしかありえない。カントが『視霊者の夢』でとった文体は、そのような苦境が強いたものである。
坂部氏は「批判」期以後のカントをふくむ近代哲学からの出口を、ほかならぬカントの前期の仕事に見られる「多元的分散の思考」に求めた。しかし、このような問題は、一八世紀半ばの西ヨーロッパに最初に生じたとはいえ、それに限定されるものではない。それは先に述べた漱石の例が示すように、明治日本にもあったことだから。実際、坂部氏は『仮面の解釈学』では、そのような日本における「近代」の経験に、近代批判の鍵を見出そうとしたといってよい。
さらにいえば、このような問題は哲学や文学に限定されるものではない。西ヨーロッパでは、十八世紀後半から十九世紀にかけて、国民国家と産業資本主義が確立した。そして、それが全世界に及び、現在もますますグローバルに深化しているわけである。そのような近代システムに対抗しようとする場合、その鍵を「前近代」に求めることはできない。求めるとしたら、それはファシズムか原理主義のようなものにしかならないだろう。坂部氏が示唆したように、近代哲学を超える鍵が、それが確立される直前に見出せるとするならば、同様に、近代国家と資本主義を超える鍵も、それらが確立される直前、つまり、十八世紀半ばの思想や社会システムに見出せるのではないか、と私は考える。
それは、経済史的な観点からいえば、資本によって組織された機械的工場生産に先行する状態、つまり、多様な職人的手仕事の結合からなるマニュファクチャーの形態である。政治的な観点からいえば、絶対主義王権に対抗して、中間集団の多元的な分散と連合からなる市民社会である。これらは前近代ではない。にもかかわらず、中央集権性と目的合理性に特徴づけられる近代システムとは異質なのである。資本・ネーション・国家という近代システムの閉域を出ようとするならば、それらが確立される直前に戻って考える必要がある。私は以上のような事柄を、他の葉によりも、坂部氏の独創的なカント論に示唆されて考えるにいたったのである。