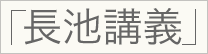石山修武と私
私が石山修武と初めて会ったのは、二〇〇〇年五月、ニューヨークで開催されたANYという会議であった。これはアイゼンマンや磯崎新を中心に、世紀末の一〇年間、毎年、世界の諸国で、哲学者などをまじえて行われた建築家の国際会議であったが、その最終回がグッゲンハイム美術館で開かれたのである。私はこの会議に常連のメンバーとして参加したけれども、少しもなじまなかった。なじもうとする気もなかった。いつも場違いな気がしていた。
建築には古代から二つの起源がある。一つは、住居である。もう一つは神殿・王宮のようなモニュメントである。偉い建築家というのは、後者にたずさわる人たちである。現在でも住居を建てている建築家も、やがて偉くなるとモニュメントを建てるようになる。ANYに集まっていたのは、だいたいそのようなタイプであり、さらに、それを難解そうな(私から見ると幼稚な)哲学的衣装で飾る人たちであった。そんなものが私に面白いわけがなかった。
私がそこにいたのは、磯崎新に依頼されたからである。磯崎さんはいわばモニュメント系の建築家の一人であったが、その中では例外者であった。彼にとっては、廃墟がモニュメントであり、したがって、モニュメントは廃墟なのだ。彼が私を会議に呼んでくれたのは、私が建築に興味があるとか、建築に貢献しうると思ったからではない。私がそれと無縁であることは、百も承知であった。彼は、私が一九八〇年ごろに書いた『隠喩としての建築』という本を高く評価してくれ、結果的に、これはMITプレスから建築論シリーズの第一回目の本として出版された。だが、これは建築論ではない。それは「隠喩としての建築」であって、実際の建築とは関係がなかった。
事実、私が引用した建築関係者は、「都市はツリーではない」を書いたクリストファー・アレクサンダーと、「都市の経済」のジェーン・ジェイコブズの二人だけである。この二人とも、都市が自然成長的に発展するものであり、人工的な都市設計が失敗に終わることを主張していた。私は特にアレクサンダーが気に入っていた。というのは、建築家による都市設計がいかに必然的に失敗するかを、鮮やかに数学的に示したからである。それは、都市設計のみならず、一般に社会の設計、経済の設計が失敗せざるをえない所以を明らかにするものだった。私が興味をもったのは、あくまで「隠喩としての建築」であった。だから、私はそれを建築プロパーの問題として考えたことがなかったのである。
そのような私にとって、ANYという会議は苦痛であった。唯一面白い、というか、ホッとしたのは、二〇〇〇年の石山修武の「世田谷村」に関する講演であった。彼を招いたのは、むろん磯崎新である。私はこの会議の最後のパネルで、一〇年間を総括して、嫌味たっぷりの講演をした。後で聞くと、この会議で一般の聴衆に最も人気があったのは、私の講演と石山さんの講演だったそうだ。どちらも甚だ明快だからだ。そして、どちらもモニュメント系建築家を否定していたからだ。
その会議のあと、私は日本に戻って、資本と国家に対抗する社会運動(NAM)を始めた。その中に建築のセクションがあり、そこに若い建築家らが参加してきた。彼らがよく石山修武について言及したので、私はあらためて彼の仕事について考えるようになった。そのとき、重要なことに気づいた。先ほどいったように、私はアレクサンダーの数学的理論に感心していたが、それ以上、考えたことはなかった。彼が「パターン・ラングエージ」について書いていることは知っていたが、それがどのような意味をもつのか考えたこともなかったのである。ところが、石山さんの「世田谷村」プロジェクトについて考えたとき、私はアレクサンダーが何を意図していたのか、突然了解したのだ。「パターン・ラングエージ」とは、どんな人でも自分の家を設計して建てられるように、建築物を構成するパーツを分類したものである。建築家はもはや建築の唯一の源泉ではない。この本があれば、クライアントは、自分の望むことを表現できるし、発展できる。建築家あるいは設計者という主体を否定したアレクサンダーは、このような考えに到達したのである。
私が気づいたのは、石山修武がやろうとしているのは、まさにこのことではないかということである。セルフビルドやオープンシステム。もちろん、石山さんはもっと徹底していて、セルフビルドを設計だけでなく、施工全体について実行しようとする。具体的にいえば、ゼネコンがやっていたような部分をも自分でやってみる。それが「世田谷村」プロジェクトである。
世田谷村建設をゼネコン抜きでやろーというのは自分でその肩代わりをしてみようという事だ。別の言い方をすれば、これまで、建築家は泥にまみれて困難なことを全てゼネコンに負いかぶせてきた。そして、ハンカチを汚さぬままに哲学や思想をつぶやいてきた。だから、人々はそれを聞く耳を持たなかった。自業自得だったのだ。私だって、実は建築を作るに際して、様々に巡らせている想い、それを厖大な浪費と言ったのだが、その浪費を得々として話したい。でも、自分でも少しは土にまみれて言わなくてはと考えたのだ。だから、これは単純なゼネコン批判ではない。自分でゼネコンの一部を演じてみなければ、ものは言えないぜと覚悟したからだ。(石山修武『設計ノート』p20)
これは、私がNAMを始めたとき考えていたことと同じである。私も「少しは土にまみれて言わなくては」と思ったのだ。爾来、私は、現実の社会や生活から離れて存在すると考えられる類の芸術や文学に対する関心をまったく無くした。ウィリアム・モリスやバウハウスがにわかに新鮮に映りはじめたのは、そのころである。
そのとき、私は石山さんから聞いたことを思い出した。冒頭に、私は石山修武と二〇〇〇年に初めて会ったと述べたが、実は、それが初めてではなかったようだ。一九七〇年代、新宿のバーで、小野二郎に紹介されて出会っていたのである。私はその時若い建築家と話したことを覚えていたが、その人が石山さんであるとはいわれるまで気づかなかった。故小野二郎は英文学者・文芸批評家であるとともに、芸術運動のリーダーで、特にウィリアム・モリスの専門家であった。モリスは今や壁紙のデザインなどではたいそう有名であるが、イギリスで最初のマルクス主義者の一人であった、というようなことはほとんど知られていない。彼はアートとクラフトを、というより、芸術と生活を分離する近代と資本主義のあり方に本質的に抵抗した人である。その意味で、私と石山さんには、モリスにかかわる縁があったといえる。
実際、そのつぎに石山さんと会ったのは、二〇〇三年、ワイマールのバウハウス大学での会議であった。バウハウスがモリスのアート&クラフトを受け継ぐ運動であることはいうまでもない。私は建築家の会議はこりごりだと思っていたが、バウハウスなら違うかもしれないと、淡い期待を抱いて出向いた。しかし、私の期待は裏切られた。彼らは本来のバウハウスとはまるで違う方向を目指していたのである。私は、ANYに出席していたときと同じように、また場違いなところにいるという感じにとらわれた。
ワイマールに滞在中、私は大学の近所のビアホールで、初めて石山さんと長く話した。彼は、私の講演を「バウハウスの連中が一番聞きたくないことをいってくれたので、うれしかったですよ」と褒めてくれた。いろんな点で、石山さんと一致するところがあったが、彼に比べれば、私は所詮、頭デッカチだという気がした。「建築家などというのは、土建屋なので、主な仕事は現場監督なんです。しょっちゅうあちこちに出かけて睨みをきかせてこないといけない」と、石山さんはいう。これは誇張でもなんでもない。私はビアホールでそのことを痛感したのである。
一杯目のグラスを飲み干したあと、石山さんは、やってきたウェイトレスに、当然のように日本語で、「ちょっと、これと同じの、持ってきて。もっと大きいやつね」と言った。身振り手振りもなしに、である。ややあきれていると、ウェイトレスは躊躇もせず、「ヤアヤア」とドイツ語で返事をして行ってしまった。きっと同じビールを注文したと誤解したのだろう、やれやれ、と思っていたら、何とウェイトレスは同じ種類のビールが入った、もっと大きなグラスを持ってきた。これには驚いた。そのとき思ったのは、おそらく、石山さんは、職人や労働者に対して、これと同じようなコミュニケーションをなしうるのだろうということである。
石山さんは、私がやっていた社会運動(NAM)についても、「あなたのようなタイプの人は人を直接組織するのには向いていないので、黒幕として影に隠れているのがよろしい。土建屋の自分は人をまとめるのが上手なので、今度NAMのようなことをやるときには、僕が表に立ってあげますよ」と、申し出てくれた。私はいつか、それができる日が来ることを願っている。