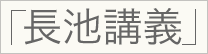天の邪鬼マサオ・ミヨシ
マサオ・ミヨシについて、先ず、簡単なプロファイルを記しておく。彼は一九二八年東京に生まれ、旧制一高・東大英文科を卒業後、一九五三年フルブライト交換留学生として渡米。ヴィクトリア朝文学を専攻して博士号を取得し、六四年には、カリフォルニア大学バークレー校で英文学教授となった。その後、日本文学についても書き始め、アメリカの日本学に画期的な影響を与えた。さらに、サンディエゴ校に移って、日本学をふくむさまざまな研究を行った。一方、一九六〇年代にバークレーで反戦運動を始めて以後、チョムスキー、サイード、ジェームソンらと並んで、行動的な知識人として知られるようになる。二〇〇九年一〇月死去。
私は一三歳年長のミヨシを、マサオと呼んでいた。それは彼ともっぱら英語で話していたからだ。日本語で話したことはほとんどなかった。私は英語を話すのは楽ではないが、英語のほうが楽な面もあったのである。たとえば、マサオと呼び捨てにすることで、日本語でなら生じるような関係の拘束から自由になる。何度か、英語を話せない日本人が混じったときに、彼が日本語で話すのを聞いたことがある。そのとき、彼の日本語が異様なほど丁寧であることに衝撃を受けた。英語の時とはまるで人格が違うのだ。言語がパーソナリティを変える、ということではない。それは、彼が一定の状況以外では日本語を話さない、ということを示すものだ。あとで知ったのは、彼が二〇年ほど日本語を話さなかった時期があるということである。
最初に話したのは、一九八〇年代の初め、東京においてである。彼が日本語で電話をかけてきたのだ。最初、私は誰かが酔っぱらって電話をかけてきた、と思った。呂律がまわらないからだ。しかし、言葉は丁重であった。フレドリック・ジェームソンがあなたに連絡するように申しましたので、と彼はいった。そのとき、私は、一九八〇年にイェール大学に滞在していたとき、ジェームソンがミヨシという面白い日本人がいる、といったのを思い出した。
その時点で、私はミヨシについて、それ以外何も知らなかった。また、電話での会話から、日系アメリカ人だと思いこんだ。確かに彼はアメリカ市民ではあったが、二世ではなかったのである。彼が東大英文科出身であることを知ったのは、大分あとである。私は一九六五年から六七年まで東大英文科の大学院にいた。ミヨシは一九六四年にバークレーの英文科教授になっているのだが、私はミヨシのことをまったく聞いたことがなかったのである。遅まきながら、腹立ちを覚えた。たとえば、東大英文科では、英文科出身で「シェークスピア全集」を翻訳した批評家、福田恒存に対して冷淡だった。彼は昔英語ができなかった、という一言で片づけられる。かつて英文科の助手をしていたと聞く、批評家磯田光一も甚だ評判が悪かった。理由は簡単だ。物書きになった者を排除するのである。ひどい話だが、物書きは学者より知られているので、まだ弊害が少ない。ミヨシのような学者が黙殺されると、その存在さえ知られないことになってしまう。
考えてみると、日本人が戦前・戦中の日本の英語教育を受けて、占領下の日本から、占領している国に渡り、名門大学の英文科(日本でいえば国文科である)で、その中でも花形のヴィクトリア朝文学の教授となるということは、ありそうもない話である。彼は、日本人として、というよりも、母語が英語でない者として、全米で初めて英文学教授となった数少ない者の一人であった。これは、快挙、というべきだろう。狭い世界であれば、話題騒然となるのがふつうだ。しかし、そのような人物が、いかにそのことが至難であるかをよく知っている人たちの間で無視されたのである。自分らにできないことをやる奴がいれば、みんなで一緒に無視しよう。こんな奴はいなかったことにしよう、というわけである。
ただ、それにはミヨシの側にも原因がある。彼は日本国籍を放棄したし、故郷に錦を飾るというような気持がまるでなかった。彼は無視されたが、彼も日本人を無視したのである。彼が二〇年間日本語を話さなかったこと、そして、日本から来た学者に英語で応対していじめたということは、本人もいうのだから、その通りだろうと思う。しかし、ミヨシはもっと厳しい環境に生きてきたのであって、その程度のことはいじめとはいえない。戦後はいうまでもないが、一九六〇年代になっても、人種差別はありふれていた。
ミヨシによると、日本人が英文学を教えることは、アメリカ人にとって、にわかには信じがたいことであったようだ。こんな話がある。バークレーの卒業式で、ある学生が連れてきた彼の父親に、大学で何をやっているのか、と聞かれ、ミヨシは、大学で庭師をやっています、と答えた。それは面白い仕事だ、と父親がいったので、学生が恐縮し、この人は英文学の教授ですよ、前に何度もいったでしょ、と大慌てで説明した。たぶんその父親も知ってはいたのだが、いざ顔を見ると、失念したのだろう。こんなときに、大学で庭師をやっています、と答えるのが、ミヨシらしいところである。この時期、カリフォルニアの日系人には庭師・植木屋が多かったのである。
一九九〇年にカリフォルニアから日本に帰る途中、コロンビア大学に立ち寄ろうとした私に、ミヨシは、ぜひエドワード・サイードに会え、君のことを言っておくから、といった。私は時間がないし会いに行くつもりはなかったが、コロンビア大学のキャンパスを歩いていると、サイードが向こうからつかつかとやって来た。一〇年ほど前にも会ったことがあるので、私だとわかったのである。彼はいきなり、ミヨシが、君が私をアタックしているといっていたが、本当か、と真顔でいう。あわてて釈明せざるをえなかった。サイードはあちこちから攻撃されているから神経過敏なのだ、冗談ではすまないよ、と思ったが、それきりで忘れてしまった。以後まもなく、サイードと親しくなったからだ。
ミヨシはそういう人柄である。子供のころリンチにあい、家に帰って母親に告げたら、あなたが殴られても当然よ、といわれたそうだ。末っ子で、親兄弟が手を焼くミヨシの「天の邪鬼」は、その後も変わらなかった。そのスケールが大きくなっただけである。マサオほど口の悪い男を見たことがないと、毒舌家のサイードがいっていたほどだ。私は、或る攻撃的なフェミニストが、ミヨシにいじめられて涙ぐんでいるのを目撃したことがある。だから、彼を忌み嫌う人が多かったのも無理はない。しかし、ミヨシは多くの人に愛された。その人たちは、彼が香港マフィアのボスのような風貌に反して、実に心やさしい人であることを知っているからだ。
ミヨシと初めて会ったのは一九八六年ボストンで、「ポストモダニズムと日本」という共同討議に参加したときである。それはミヨシとハルトゥニアンによって組織されたものであった。この時期、バブル時代の日本人のありようが、アメリカで注目を浴びていた。日本はアメリカの経済的ヘゲモニーを脅かすだけでなく、その文化においても最先端の傾向を示しているように見えたのである。「日本」はポストモダニズムの代表的な例となっていた。この会議には、ミヨシに呼ばれて、日本研究者以外の学者が大勢参加していた。
私が初めて会ったとき、ミヨシはすでに英文学をやめていた。先述したように、私はそれ以前の彼を知らなかった。なぜミヨシは英文学をやったのだろうか。彼が英語・英文学を勉強したのは日米戦争下である。英語は「敵性言語」であり、旧制高校といえども、公然と英語・英文学をやる雰囲気はなかった。そのため、彼は何度か袋だたきにあった、という。こっそりとではなく、これ見よがしに英語を勉強していたからだ。英語・英文学の勉強は、日本の社会に対する反抗以外の何ものでもなかった。
ミヨシの中の「天の邪鬼」は、戦後においても健在であった。戦後、人々がみな左翼に転向したときに、彼はそうしなかった。もし左翼であったら、占領下時代に、アメリカに留学したりはしないだろう。しかし、ミヨシは、戦前からの日本社会に対して左翼以上に強く反撥していた。アメリカに渡って日本国籍をあっさり捨ててしまったのも、そのせいであろう。彼は日本を拒絶していた。
ミヨシが左翼になったのは一九六〇年代半ば、カリフォルニア大学バークレー校においてである。正教授となったことで、一応目標を達成したということもある。しかし、最大の理由は、このとき、新たな戦争に出会ったことだ。それは深化しつつあったベトナム戦争である。今度は、ミヨシはアメリカ市民として、国家に対抗し始めたのである。さらに、バークレーにいたことが重要だった。そこは、一九六八年に全米の新左翼学生運動の拠点となった場所である。ミヨシは一九六六年に客員教授としてやってきたチョムスキーと知り合い、反戦・市民権運動に本格的に乗り出した。
それとともに、彼は従来のアカデミックな英文学のやり方、つまり、文学を政治と区別して扱うという中立的な態度を否定しはじめた。彼が近代日本文学を読み始めたのも、このころからである。特に、三島由紀夫の自決がきっかけだった。一九七四年に、近代日本の小説に関する書物『沈黙の共犯者たち』を出版した。これは、アメリカの日本文学研究における一事件であった。アメリカの日本文学研究は、ある意味で占領軍出身者がやっていたようなものである。彼らは日本語が十分に理解できないが、日本人より西洋文学を知っているということでやってきた。日本人も彼らを崇めていた。そのような「沈黙の共犯」を破れるのは、日本人にしてアメリカの英文学教授である、ミヨシだけである。ミヨシが、アメリカで新世代の日本学者に圧倒的な影響力をもったのは当然である。しかし、日本では、この本は翻訳されず話題にもならなかった。そして、占領軍上がりの日本学者がいまだに尊敬されている。
ミヨシがすごいと思うのは、あれほど熱心にやってきた英文学研究を放棄してしまったことだ。彼は一九八六年にカリフォルニア大学サンディエゴ校に移り、いわば何をやってもいいようなポストを得た。といっても、専門を捨てるのは誰でも恐ろしいはずである。というより、そんなことを考えもしないのがふつうだ。たとえば、チョムスキーはどんなに政治的活動に奔走していても、言語学を捨てていない。さらに、ミヨシがすごいのは、つぎに日本学をも捨ててしまったことである。彼は、そこにいれば安泰を保証されるような場をあっさり放棄して、関心を引く別の場に移動する。ミヨシのような人を私は他に知らない。
私は一九九〇年から、コロンビア大学比較文学科で教えるようになった。ほぼ隔年に一学期の割合で教えた。他の大学でも教えた。それで、ミヨシとは、さまざまな会議・講演会などでたびたび会うようになったのである。また、編集していた季刊誌『批評空間』のアドバイザリー・ボードに、サイードやジェームソンらとともに入ってもらった。この間のつきあいで、私はミヨシから多くのことを学んだ。
ミヨシには先見の明がある、と思ったことが何度かある。一つは、「大学の終り」に関して、である。九〇年代の前半に、ミヨシはその問題を考え、ヨーロッパ中世以来の大学の歴史を分析していた。彼から、日本の大学はどうか、と聞かれたとき、私は、ひどい、と答えた。しかし、そのとき私は、彼が考えていることが実はわかっていなかったのである。私は日本の閉鎖的なシステムに比べて、アメリカの大学は開かれている、と思っていた。学生も教師も自由に移動している。早い話が、私のような者を招いて好きなようにさせるのは、アメリカの大学だけではないか。
だが、私はその裏側で進行していた事態に気づかなかった。アメリカでは一九八〇年代に、大学に特許権の所有が認められるようになった。以来、大学が企業化したのである。たとえば、科学者は学会に発表する前に特許権を申請する。このやり方が自然科学だけでなく、他の領域に及んでくる。人文学も同じような基準ではかられるようになる。大学は、学生という顧客にサーヴィスを提供する企業となる。教師は目に見える業績を短期間に示さなければならない。学会や共同研究セミナーが頻繁に開かれるのは、そのためである。大学院生も同様だ。博士論文にはすぐに出版できるようなテーマを選び、それを流行の方法で処理する。
ミヨシが「大学の終り」を告げたとき、私は、そういうものかな、と思っただけであった。彼がいうことを実感したのは、二〇〇〇年以後日本で、国立大学の「民営化」(独立法人化)がなされるようになってからだ。もちろん、私立大学でも同じような変化があった。日本の大学改革はアメリカのやり方を真似たものであったから、結果も同じである。というより、もっとひどい。それ以後、日本の大学は急激に終ってしまった。たとえば、短期間に計測できるような成果を出せ、というと、特に人文系の学問はやっていけない。その証拠に、文学部はつぎつぎと消えたのである。
もう一つの例は、「日本は面白くない」(Japan is not interesting)というミヨシの講演である。日本のバブルの崩壊が顕著になったころであった。彼はハーバードかどこか東部の大学で講演して、その帰りにニューヨークにいた私のところに立ち寄って、その講演の趣旨を聞かせてくれた。それはバブルの崩壊とともに、日本的経営とその背景にある日本文化一般への関心が終ったということである。私はその後、アジア学会で、「日本は面白い」という講演をした。といっても、ミヨシ批判ではない。正確にいうと、私の講演の題は、”Japan is interesting because Japan is not interesting”なのである。そこで、私は日本の「伝統」について語った。ただし、禅や茶道や浮世絵ではなく、宇野弘蔵をはじめとするマルクス主義の伝統である。
しかし、私はミヨシの「日本は面白くない」という講演が含意していたことに気づかなかった。「日本は面白くない」というのは、かつて英文学を放棄したように、日本文学・日本学を放棄するということを意味していたのである。実際、彼はそうした。日本学を放棄しても、新たにやるべきことはいくらでもある。彼は環境の問題について本格的に考え始めた。さらに、彼は大学もやめてしまった。「大学で教えることは面白くない」と考えたのだろう。たとえそうでも、これまで長年やってきたことを放棄するのはもったいない。誰もがそう思うときに、さっさとやめてしまう「天の邪鬼」がミヨシである。ミヨシのように無鉄砲なお手本がなかったら、私も文学批評をやめたり大学を辞めたりすることはなかったかもしれない。
一昨年の秋、ミヨシは新妻とともに、東京郊外の私の家を訪れた。現在の生活を楽しんでいる、なぜ長く教師などやっていたのかわからない、と彼はいった。今後の抱負をあれこれと語っていた。今年も来日する予定があった。しかし、六月末に、突然、遺書のようなEメールが届いた。末期癌が判明したので、残念ながらもう会うことはできない、という趣旨であった。これは複数の日本人に宛てられていたから、日本語の手紙だった。彼の日本語の文章を読んだのは初めてである。その日本語は話し言葉と同様に、どこかぎこちない古風なものだった。最後に、「まあ、生だの死だの今別に考える事も在りませんが、死んだ後で郵便さへあれば僕の消滅の経験をお知らせします。どうぞお元気で」とあった。ミヨシらしい、と思う。
末期癌の判明は唐突であったとしても、ミヨシは前から死を予期していたと思う。サンディエゴで彼の学生であった吉本光宏のインタビューによる自伝『抵抗の場へ』(2008年)を出版したし、同時に、エリック・カズディンによる編集で、「Trespasses」という題の評論集(ジェームソンの序文がついている)の刊行を準備していた。この本を読むと、ミヨシの主要な仕事が概観できるようになっている。『抵抗の場へ』には「あらゆる境界をこえるために」という副題がついており、また、trespassとは境界を侵犯するという意味である。ミヨシは文字通り、生涯にわたって、境界を侵犯した人であった。ふと、私は思う。ミヨシのことだから、死後、生死の境界を侵犯して、「消滅の経験」を知らせてくれるかもしれない、と。