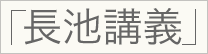厄介なる主体1 政治的存在論の空虚な中心
スラヴォイ・ジジェク 著
本書は、文字どおり「厄介な主体」、つまりデカルトの「コギト」をめぐる、現代思想家による論考集である。
デカルト的主体の批判はポストモダニズムに共通する。互いに一致するはずのなさそうな諸学派が、この点では一致している。啓蒙(けいもう)的近代を否定するニューエイジ神秘主義者やエコロジストから、デカルト的主体から「存在」に向かったハイデガー、コギトを言説的虚構とみなす脱構築主義者、対話を通した間主体性を提唱するハーバーマス、コギトに男性的な支配を見いだすフェミニスト……。
しかし、著者ジジェクによれば、デカルトのコギトは「透明な自己」という安穏なイメージとはほど遠い。デカルトはあとで、懐疑を決行する前に発狂の危険に備えたことを書いているが、実は、途中で発狂したことに気づかなかったのかもしれないのである。ハイデガーは、デカルトのコギトが「存在」の裂け目から来ることに気づかなかった。
では、こうした「反デカルト的主体」の大合唱は何を意味するのか。端的にいって、「懐疑」の放棄である。つまり、現在のグローバルな資本主義とともに生じた事態、あるいはリベラル民主主義に対する、懐疑の放棄である。たとえば、多文化主義者は、「超越論的主体」に対抗して、女性という主体、ゲイという主体、民族という主体などの主体の多様化を歓迎する。
だが、多文化とは、グローバル資本主義による均質化の結果にすぎない。多文化主義は、資本主義的現実を政治経済的な視点から考えることを放棄させる。それこそ、「デカルト的主体」の放棄にほかならない。
著者は、アルチュセール派から出発してさまざまな地点に達した四人の思想家(ラクラウ、バリバール、ランシエール、バディウ)の政治哲学を吟味しつつ、グローバル資本主義とリベラル民主主義に対する左翼的な対抗の可能性を探ろうとする。その中で、著者はバディウに対して最も好意的である。それはバディウがポストモダニズムを最も拒絶しているからである。
柄谷行人 |2005.10.30 |朝日新聞 書評欄掲載