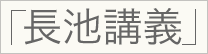吉本隆明の時代
絓(すが)秀実 著
本書は「吉本隆明論」というよりも、その「時代」、特に1960年の前後10年ほどの時期を扱った歴史書というべきものである。なぜそれが吉本論として語られるのか。この時代が、吉本隆明という批評家がヘゲモニーを確立していった時期だからである。
それ以前には、さまざまなタイプの知識人がいて、吉本はその中の一人にすぎなかった。そのような知識人らがそれぞれの課題と動機をもって一堂に会したのが、1960年安保闘争という舞台であった。しかし、この過程で、吉本は他の者を残らず駆逐してしまった。それ以前と以後では思想の風景が一変してしまったのである。なぜこんなことがありえたのか。
この問題に関して、著者は二つの参照例をもってきた。一つは、安保闘争をフランスのドレフュス事件との類推で見ることである。そこから、その頃の日本になぜ自由浮動的な「革命的」知識人が出現したのかを照明する。もう一つは吉本隆明を、戦後フランスの知的世界に君臨した哲学者サルトルとの類推で見ることである。なぜサルトルは知識人として別格の地位を得たのか。その理由の一つは、彼が小説家であり、けっして大学の教授にならなかったことだ。つまり、彼は「呪われた詩人」という系譜に属していたのである。
吉本隆明も同様であった。彼はむしろ、「呪われた」負の部分を栄光へと逆転することによって、勝利したのである。しかし、著者は吉本隆明の「勝利」にも、勝者によって作られた歴史にも関心をもっていない。実際、吉本が勝者であるとはいえない。彼に覇権を与えた高度資本主義経済が、彼自身を呑(の)みこんでしまったからだ。それを対象化するには、吉本が消去してしまった諸視点が必要である。
著者はその鍵を、吉本隆明の罵倒(ばとう)の下に消されていった敗者(花田清輝・武井昭夫・丸山真男など)に見いだそうとしている。これらの考察は新鮮で啓発的である。本書は“1960年”だけでなく、戦後日本史に関する通念を根本的に変える、スリリングな歴史書である。
柄谷行人 |2009.3.1 |朝日新聞 書評欄掲載