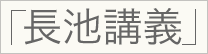民主主義への憎悪
ジャック・ランシエール 著 | 松葉祥一 訳
一般に、民主主義というと、代表制(議会制)と同義だと考えられている。しかし、モンテスキューは代表制と民主主義を峻別(しゅんべつ)した。代表制とは 貴族政あるいは寡頭政の一種であり、選挙によって選ばれた有能なエリートが支配する体制である。一方、民主主義の本質は、アテネにおいてそうであったよう に、くじ引きにある。デモクラシーとは、デモス(民衆)が、すなわち、「とるにたらない」(誰でもよい)者が統治する体制なのである。
プラトンのような哲学者はデモクラシーの中にあって、それを憎悪した。この「民主主義への憎悪」は現在まで続いている。たとえば、日本では、民主主義は しばしば、「戦後民主主義がもたらした、行き過ぎた平等」といったぐあいに、否定的に言及される。それはまた、大衆消費社会・福祉政策・ポピュリズムなど とも結びつけられる。著者が批判する、今日のフランスの言論界の論調も似たようなものである(訳者による詳しい注は、この文脈を理解するのに役立つ)。
しかし、今日、民主主義を唱道する人たちも、実はこの「憎悪」をひそかに抱いている。彼らは民衆の意見を汲(く)みとるといいつつも、見識のある代表者 (政治家・知識人)がリードするのは当然だと考えている。そうでないと、衆愚政治に陥ってしまう、と。彼らが議会制民主主義を称賛するのは、それを通し て、代表者が民衆を啓蒙(けいもう)し、合意(コンセンサス)を形成することができるからだ。ゆえに、議会制民主主義は実質的に、寡頭政にほかならない。
一方、民主主義の問題をプラトンにさかのぼって根本的に問い直す著者は、このような発想を斥(しりぞ)ける。彼は民主主義を積極的に肯定する。といって も、民主主義は制度ではないし、合意を形成する手段でもない。それは、これまで公的な領域から排除され、「言葉をもたない」とされてきた者らが、「不合 意」を唱え、異議を申し立てる出来事を意味する。そこにこそ、「とるにたらない者」による統治、つまり、デモクラシーが存在するのである。
柄谷行人 |2008.9.21 |朝日新聞 書評欄掲載