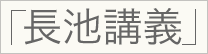暴力はどこからきたか ― 人間性の起源を探る
山極寿一 著
戦争にいたるまでの人間の攻撃性に関しては、コンラート・ローレンツによる有力な説があった。動物の場合、攻撃性とその抑止機構にバランスがとれていたのに、人間の場合、武器の出現のために、それができなくなったというものである。また、この考えは、人間が狩猟生活から武器を発展させ、それが同類への攻撃に及んだという説ともつながっている。
しかし、このような説は、近年の動物行動学や人類学の研究のなかでくつがえされた。たとえば、動物の同種間の殺害が多く報告されているし、狩猟民は一般に争いを避けることが明らかになっている。狩猟と戦争は別だ。戦争は、定住と農耕以後の現象なのである。さらに、最近では、原始人は狩猟者というよりも、逆に捕食される者であり、その体験を通して協働する体制を作るようになったという説もある(ドナ・ハートとロバート・サスマン『ヒトは食べられて進化した』)。
このように攻撃性の問題を根本的に見直す流れの中に、本書もある。著者の基本的な視点は、動物は、たんに機械的に攻撃性を発露させているのではなく、限りある資源(食糧と交尾の相手)をめぐって、いかに相手と共存するかを模索してきている、というものだ。たとえば、近年、ゴリラなど霊長類の間で子殺しが多いということが観察されているが、そこから逆に、著者は、オスによる子殺しを避けようとすることが、霊長類の社会性を作ってきたのではないかと考える。同様に、インセスト(近親姦(かん))の回避も、性的な競合を緩和するためになされる、とみてもよい。
食と性に関する同種間の葛藤(かっとう)は避けられない。それを機械的に解決するような本能は与えられていない。類人猿たちは状況に応じて、さまざまな社会的な機制を作って対応してきたのである。ゴリラは食べ物を分け合って、一緒に食う。チンパンジーやボノボには互酬交換が見いだされる。また、彼らは争った後に、積極的に仲直りしようとする。そのような類人猿のふるまいをみるとき、われわれは励まされる。
柄谷行人 |2008.2.17 |朝日新聞 書評欄掲載