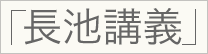文化人類学とわたし
川田順造 著
本書は「文化人類学とは何か」を問う本であるが、表題が示すように、それは「わたし」とは何かを問うことと切り離せない。文化人類学は、石田英一郎が、アメリカでクローバーらの総合人類学の考え方に共鳴し、東京大学教養学科に新設したものだ。それ以前は、民族学と呼ばれていた。文化人類学は、「アメリカ直輸入の学問」なのである。著者は新設学科の2年目に入った、「文化人類学の純粋培養」の世代であった。著者はそのことに疑いを抱きつつ、文化人類学者として生きてきた。とはいえ、疑いが否定になったわけではない。著者はそれによって、文化人類学あるいは総合人類学を「わたし」のものとしてきたのである。
文化人類学は確かに「アメリカ直輸入の学問」である。が、実は、それ以前の民族学も西洋直輸入の学問であった。そして、誰よりもそれを摂取しながら斥(しりぞ)け、自前の経験にもとづく学問を志向したのが、柳田国男である。彼はそれを「新国学」と呼んだ。だが、重要なのは、柳田が、民俗学を広義の自然史、あるいは、文字に記録されない歴史の方法と見なしたことである。
この意味で、かつて名著『無文字社会の歴史』(1976年)を刊行した著者に最も近いのは、柳田であろう。だが、同時に、著者は、「柳田民俗学が志向したような探求を、世界大の視野で行ってゆくこと」を提唱している。また、ヒトとその文化を自然史の一過程として見る立場を徹底させて、ヒト中心主義を超えた「種間倫理」を提唱する。
著者にとって、文化人類学はつねに現実の社会と歴史にかかわる行動である。一方で、ダホメ(アフリカ)の世界遺産保護、修復の仕事にたずさわってきた。他方で、毎年8月15日に靖国神社に行き、人々や出来事をしらべることを続けている。また、江戸からの連続性をもつ東京下町の人たちから話を聞くことを続けている。それらは、明治以後の国家的歴史に対して、いわば「無文字社会の歴史」に迫る方法にもとづいて対抗することだといえる。
柄谷行人 |2008.1.20 |朝日新聞 書評欄掲載