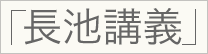廣松渉 ― 近代の超克
小林敏明著
廣松渉は、マルクス主義の哲学者として知られている。しかし、読者の中には、つぎの点でとまどいを覚えた者が少なくないだろう。一つは、死語化した漢語の異様なほどの連発である。第二に、晩年に朝日新聞に載せたエッセーで、「日中を軸にした東亜の新体制を!」と提唱したことである。どうして、これらが「マルクス主義」と関係するのだろうか。
本書で、著者は、廣松の仕事のエッセンスを手際よく解説するとともに、以上のような疑問に答えようとした。それは廣松を、「日本の近現代思想史の流れの中に位置づける」ことである。中でも重要なのは、西田幾多郎や京都学派哲学者とのつながりである。廣松は京都学派に対して、反発と同時に強い共感をいだいていた。おそらく、このことを知るだけで、多くの疑問が氷解するはずである。
京都学派は「近代の超克」を唱えた。その「近代」の中には、資本主義や国民国家だけでなく、マルクス主義も入る。廣松も「近代の超克」を目指した。しかし、彼にとって、マルクス主義こそ「近代の超克」を実現するものであり、その点で、京都学派を批判した。だが、「近代の超克」という志向においては、同じである。実際、廣松の「マルクス主義」では、近代哲学・近代科学の「超克」に焦点があてられている。
著者は、「近代の超克」はたんなる近代の批判ではない、という。それは、前近代的な場にある者が、一方で、近代を志向しつつ、さらに、他国で実現された近代を批判するという二重の課題を追求することだ。一言でいえば、後進国のインテリに特有の思考である。その典型は、先進国イギリスを念頭において考えたドイツの哲学者、ヘーゲルである。ヘーゲルが西田幾多郎や廣松渉に甚大な影響を与えた理由もそこにある。著者が指摘するのは、彼らに共通する点は、たんに後進国日本に位置しただけでなく、日本の中でも辺境に位置したということである。西田や廣松の奇妙な「文体」は、そのような二重のねじれた意識に発している。
柄谷行人 |2007.8.26 |朝日新聞 書評欄掲載