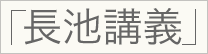獄中記
佐藤優 著
本書は、かつて「外務省のラスプーチン」と呼ばれた著者が起訴され、独房に拘置された五一二日間に書いた膨大な読書ノートや書簡を圧縮し編集したものである。著者はこの事件についてすでに何冊も本を出している。本書でも当然それについての言及があるが、中心は何といっても、ヘーゲルの『精神現象学』の精読から始まる読書ノートである。そこには、どんな優れた知識人のノートにも見いだせない類(たぐい)の、驚嘆すべき知性の活動がある。
それは、著者が従事していたインテリジェンスという仕事に関係があるだろう。インテリジェンスという語には、知性と諜報(ちょうほう)という意味がある。諜報は、いわゆるスパイ活動よりも、むしろ誰でも入手できる情報を深く分析することが中心であるから、結局、知性の問題だということになるかもしれない。しかし、諜報という語からはやはり、知性というのとは違った外向性・行動性が感じられる。
実際、本書の「知性」が魅力的なのは、それが外交的・行動的だからである。通常、それは知的であることと矛盾する。だが、著者の場合、通常なら矛盾するようなことが、平然と共存するのだ。たとえば、著者は「絶対的なものはある、ただし、それは複数ある」という。そこで、日本国家と、キリスト教と、マルクスとがそれぞれ絶対的なものとしてありつつ、並立できるのである。
本書を読むと、どうしてこのような知性が出現したのか、考えずにいられないだろう。ひとまずいえるのは、著者自身がたえずそれを問うているということだ。独房で読む本はむしろそのために選ばれている。著者の考えに最も適合するのはおそらく、最初に選んだヘーゲルの『精神現象学』であろう。それはあらゆる命題(テーゼ)を肯定すると同時に否定するものだ。その意味で、「絶対的なものはある、ただし、それは複数ある」という著者の考えは、まさに弁証法的である。それは著者がヘーゲルから学んだものではない。著者がヘーゲルに自分を見いだしたのである。
柄谷行人 |2007.1.28 |朝日新聞 書評欄掲載