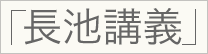資本主義に徳はあるか
アンドレ・コントスポンヴィル 著 | 小須田健、C・カンタン 訳
われわれは、ある現象を体験するとき、たんに知的に認識するだけではない。同時に、それに対して道徳的な判断をし、また快・不快のような情動を感じる。これらを区別することは難しい。そこで、あるものを知的認識(科学)の対象とするには、それに対する美的判断や道徳的判断をカッコにいれなければならない。一方、それを美的判断の対象とするには、真偽の判断や道徳的関心をカッコに入れなければならない。たとえば、これは虚構だとか、主人公が悪いといっていたのでは、小説を読めないであろう。このような領域の区別とその根拠をはっきりさせたのが、カントの「批判」であった。
本書で著者がやっているのも同じような仕事、つまり「批判」であるといってよい。ただ、著者は領域を「秩序」と呼び、またそれをつぎのように四つに分けている。第一に、経済―技術―科学的秩序。第二に、法―政治の秩序。第三に、道徳の秩序。第四に、愛(倫理)の秩序。
これらはそれぞれ異なる秩序にあり、それぞれに固有の原理をもっている。ゆえに、それらは混同されてはならない、というのが著者の主張である。しかし、これらの秩序は別々にあるのではない。どんな個人も、同時に四つの異なる秩序に属している。だから、それらを混同してしまうのも無理はない。
その中でも最も危険なのは、経済や政治の秩序と道徳の秩序の混同である。たとえば、ひとびとが平等であるべきだという考えは、道徳の秩序に属するが、それを経済的に実現しようとすると、経済を破壊することになる。その結果、平等そのものが実現されなくなるだけでなく、道徳的な理念が嘲笑(ちょうしょう)的に否定されるようになる。それは旧ソ連の社会主義経済とその崩壊がもたらした事態である。
しかし、経済や政治の秩序と道徳の秩序の混同は、今日でも別の形で生じている。たとえば、道徳性が政治の領域にもちこまれている。「聖戦」とか「正しい国家」のような考えがその例である。
一方、「企業倫理」というような言葉がよく使われている。まるで経済が道徳的でありうるかのように。しかし、個人のレベルに存する道徳性や愛を、集団である企業に見いだすべきではない。企業は何よりも利潤を追求しているのであり、そうでなければ成り立たないのだ。
といっても、著者が目指しているのは、経済や政治を道徳性からまもることではない。むしろ、道徳性を経済や政治からまもることである。いいかえれば、道徳や愛の秩序を高い理念としてあくまで保持しつつ、現実的な経済と政治に即しながら、それらを徐々に忍耐強く変えていこうということである。このような著者の立場は、一言でいえば、「自由社会主義」ということになるだろう。それは新自由主義と福祉国家主義の両方を批判するものである。前者は道徳性を欠いており、後者は経済の秩序を無視している。著者はそのような事柄を、普通の人たちに向けて、明晰(めいせき)に且(か)つ平易に語ろうとしている。
柄谷行人 |2006.10.22 |朝日新聞 書評欄掲載