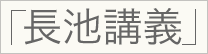漱石という生き方
秋山豊 著
近年私は文芸評論を読む気がしない。それらは新しく見せようと奇をてらい、新知識を動員しているが、どれもこれも陳腐である。そもそも書いている人が何のために文学をやっているのかさえわからない。とくに漱石論などはおびただしく出版されているが、手に取るのもうんざりだ。ところが、この漱石論は読みはじめると、やめられなくなった。非常に新鮮なのである。
本書の特徴はまず、批評家や学者からの引用がほとんどないという点にある。といっても、それは主観的に感想を述べたものではない。その反対に、本書は、漱石の創作・評論・談話・書簡にいたるまで、すべてを自筆原稿から検討し周到に読み込んだのちに、書かれているのである。どうしてこういうことがありうるのか。タネを明かせば、著者はかつて『漱石全集』を編集した編集者であり、引退した後にこれを書いたのである。
たとえば、漱石の『心』という作品は、『こゝろ』または『こころ』と表記するのが正しいと考えられてきた。が、自筆原稿にあたって調べると、『心』が正しい。国語の教科書にも載っている有名な作品に関して、このような誤解がまかりとおってきたのは、むしろ驚くべきことだ。この一例からでも、同様の誤解が、作品の読みに関しても数多く存在するだろうということが予想できるはずである。実際、自筆原稿をふくむテクストの丹念な検証にもとづく本書は、かつてない深い読みをもたらしている。
しかし、本書を新鮮にしているのは、作品の新しい読解というよりも、むしろ作品に対する姿勢である。それは今や希有(けう)なものだ。「私の希望は、漱石に寄り添って、よく彼の言葉を聞き取りたいということに尽きる」と著者はいう。これは謙遜(けんそん)ではないし、レトリックでもない。本書は、研究者や批評家のような野心をもたず、漱石に寄り添いつつ生きてきた人のみが書けるような本である。おそらく「漱石という生き方」という題は、そのことを最も的確に表しているといえるだろう。
柄谷行人 |2006.6.11 |朝日新聞 書評欄掲載