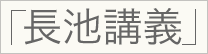思索日記1 1950−1953
ハンナ・アーレント 著
本書は、アーレントが1950年から73年にいたるまで書いたノートを編纂(へんさん)した本の第1巻である。ここには50年から53年にかけてのノートが収録されているが、それは著者が『全体主義の起原』を出版したのち、『人間の条件』を書くにいたるまでの思索の跡を示している。
多彩な内容をもったこれらのノートに一貫しているのは、いわば「全体主義の起源」を近現代においてよりも、古代においてみようとする志向だ、といってよい。全体主義は西洋の哲学・宗教に反するものではなく、むしろそこにこそ胚胎(はいたい)する。一口でいえば、それは、人間の「複数性」を認めない思考である。
たとえば、西洋の哲学は内省、つまり、自己との対話にはじまった。それは、実際に他人と話すこととは違っている。他人との対話がどこに向かうか予測不可能であるのに対して、自己との対話は確実であり、絶対的な真理に向かうことになる。この意味で、西洋の哲学的伝統は、異質な他者を排除することによって成立している。
アーレントは、こうした思考の伝統を社会認識においても見いだす。たとえば、マルクスは古典派経済学にもとづいて、「労働」を根底におき、生産物の価値が交換過程において見いだされる次元を軽視した。それは、交換という「活動」の次元、つまり、予測不可能な他者との関係の次元を見ないことである。こうして、「労働」を根底におくことが、複数性(他者性)を否定する「全体主義」に帰結したのである。
このような伝統の中で例外的であったのは、複数の相異なる人間の間で、趣味判断の普遍性がいかに成り立つかを考えたカントである。ここから、カントの『判断力批判』を政治哲学として読む、アーレント独自の考えが出てきたのである。のみならず、そこに、彼女は、複数性を前提するような社会主義への鍵を見ようとした。総じて、本書には、のちに本としてまとめられたときには消えてしまう、豊かで多様な思考がとどめられている。
柄谷行人 |2006.5.14 |朝日新聞 書評欄掲載