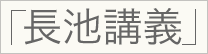抗争する人間〈ホモ・ポレミクス〉
今村仁司 著
本書は、社会哲学者として知られた著者の、これまでの仕事を集大成するような力作である。
著者はくりかえしこう語る。共同体や国家には根底に暴力がある。それらの秩序は、ある一人の人間を犠牲にすることによって成りたっているからだ。そのことは、平等が達成されるような未来の理想社会においても変わらない。このような暴力の源泉には、他人の承認を求める人間の欲望がある。それは他人に優越しようとする社会的欲望であり、このために相互的な競争が生じ、そこからは誰か一人を排除することによってしか安定した秩序が形成されないのである。
これは、著者が若い頃から、ルネ・ジラールの欲望論を引いて主張していた理論である。このような認識は、理想主義が強かった時代においては意味があったと私は思う。なぜなら理想主義がうらはらに残酷な社会体制を作り出すケースが各所に見られたからである。
だが、ソ連邦が崩壊し、一切の理念をあざ笑うシニシズムが蔓延(まんえん)したのちに、さらに国家が露骨な暴力性を示している時期に、このような主張は何を意味するのだろうか。
著者は、究極的には、暴力に依拠する制度を廃棄する可能性があると考える。それは「覚醒(かくせい)倫理」、すなわち、「こうした欲望との批判的対決であり、対他欲望を消し去るための闘い」によってもたらされる。しかし、これは宗教的悟達に似ている。歴史の原動力を社会的欲望(仏教でいえば煩悩)に見いだす理論、あるいは、自己意識から出発する理論は、そのような解決(解決不能)しか見いだせないのである。
実際、ジラールは(ある意味でラカンも同様であるが)人間が解決不可能な困難をもつことを執拗(しつよう)に示すとき、暗黙裏にカトリックという救済装置をもっていた。人間がいかに無力であるかをいえばいうほど、信仰による救済が示唆される。つまり、根本的には保守派の議論なのである。著者の今村氏もそうなのか。あるいはそうではないのか。本書では、その辺がまだ不明瞭(ふめいりょう)である。
柄谷行人 |2005.4.17 |朝日新聞 書評欄掲載